放課後等デイサービス支援事業は、事業所で働く支援者の方々とともに、子どもたちにとってのより良い支援を考えていく京都市の事業です
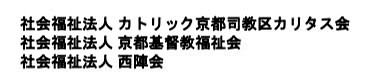
書籍紹介
参考になりそうな本を集めてみました。
なるべく京都市が所蔵している本から紹介しており、京都市図書館にリンクしています。
LDの子が見つけたこんな勉強法
野口 晃菜/編著 -- 合同出版 -- 2023.9 -- 175p
「学び方」はひとつじゃない!
板書をICTにまかせて聞くことに集中、別室で1人の演奏会…。学校での勉強の仕方やストレスなどで悩みを抱えている人たちが、これまでやって来た工夫37を紹介。LD当事者と家族へのインタビューも収録。
#LD #学習障がい
怒られの作法
草下 シンヤ/著 -- 筑摩書房 -- 2023.4 -- 236p
日本一トラブルに巻き込まれる編集者の人間関係術
クレーム、炎上、人付き合い…揉め事ぜんぶ平気になる! 裏社会を渡り歩いてきた作家・編集者が、自分が怒られているのに、まるで他人事のように相手の怒りを受け流す、究極の「他人と向き合う技術」を明かす。
#コミュニケーション #人間関係
発達「障害」でなくなる日
朝日新聞取材班/著 -- 朝日新聞出版 -- 2023.11 -- 218p
こだわりが強い、コミュニケーションが苦手といった発達障害の特性は本当に「障害」なのか。人間関係などに困難を感じる人々の事例を通し、当事者の生きづらさが消える新しい捉え方、接し方を探る。『朝日新聞』連載を書籍化。
#発達障がい
逆境に克つ力
宮口 幸治/著 -- 小学館 -- 2023.4 -- 190p
親ガチャを乗り越える哲学
親ガチャは運命か? 言い訳か? 「ケーキの切れない非行少年たち」の著者と気鋭の哲学者が、逆境を乗り越えるための心のもち方や人生を切り開く力のつけ方を、哲学・心理学・精神医学の観点から具体的に提唱する。
#人生訓
アスペルガー症候群の子どもたち
飯田 順三/編著 -- 合同出版 -- 2014.4 -- 148p
子どものこころの発達を知るシリーズ
その病像論の誕生から消滅まで
アスペルガー症候群(高機能自閉症スペクトラム)の原因や病態に関する主要な研究を整理し、治療や支援のあり方についてまとめる。成人のアスペルガー症候群に対する支援の実際も紹介。
#アスペルガー症候群 #ASD
図解でわかる障害児・難病児サービス
二本柳 覚/編著 -- 中央法規出版 -- 2023.11 -- 251p
障がい児・難病児を支える制度から、サービスの使い方、子どもと保護者への支援方法までを、豊富な図表とともにわかりやすく解説する。児童福祉サービスの実践事例も紹介。
#心身障がい児 #難病 #児童福祉
ADHDの子どもたち
岩坂 英巳/編著 -- 合同出版 -- 2014.6 -- 156p
子どものこころの発達を知るシリーズ
最新の医学的知見を基として、特別支援教育や発達障害者支援などの社会的動向も踏まえたうえで、ADHDのある人をいかに理解するかについて考えるほか、彼らへのかかわりをどうしていくかを、具体的に提案する。
#ADHD #注意欠陥多動性障害
図解コーチングの「基本」が身につく本
本間 正人/著 -- 学研パブリッシング -- 2012.9 -- 173p
メンバーの心をつかみ、チームを思い通りに動かす即効コミュニケーション35
コーチングの基本をマスターすれば、人間関係がよくなり、仕事の生産性も高まる! 「コーチング」や「ほめ方、叱り方、励まし方」のエッセンスを、わかりやすい図解と具体的なケースで紹介する。
#経営管理 #コーチング
10代から身につけたい
ギリギリな自分を助ける方法
井上 祐紀/著 -- KADOKAWA -- 2020.5 -- 191p
「自分は守られるべき存在だ」 精神科医が教える、“頼る”ことからはじめるセルフケアとは? 友だち、恋愛、家族、自分自身…。日々の生活の中で感じる、生きづらさを解決するためのヒントを伝える。書き込みページあり。
#カウンセリング #セルフケア
弟は僕のヒーロー
ジャコモ・マッツァリオール/著 -- 小学館 -- 2017.8 -- 285p
僕は5歳のとき、パパとママから弟が生まれると聞かされ、大喜びした。しかも、どうやら弟は「特別」らしい。僕はだんだん「特別」の意味を知り…。19歳の青年が、ダウン症候群の弟との生活を描いた愛と成長の記録。
原タイトル:Mio fratello rincorre i dinosauri
#ダウン症候群 #きょうだい児
ニューロダイバーシティの教科書
村中 直人/著 -- 金子書房 -- 2020.12 -- 5,133p
多様性尊重社会へのキーワード
人間理解の新たな視点である「ニューロダイバーシティ」の入門書。その概念をはじめ、脳や神経由来の違いという「内側のメカニズムの違い」から人を理解するとはどういうことなのか等について説明する。
#発達障がい #脳 #神経
13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル/著 -- ダイヤモンド社 -- 2017.11 -- 214p
性とジェンダーの多様性について学べるパーフェクト・ガイド。約40人のLGBT+のインタビューを収録し、図やイラストも豊富に使ってLGBT+をわかりやすく説明する。用語解説付き。
原タイトル:The ABC's of LGBT+
#性 #ジェンダー
正解のない教室
矢萩 邦彦/著 -- 朝日新聞出版 -- 2023.3 -- 270p
自分で考える力を鍛える
リベラルアーツ(自由に生きるための技術)を学んで、自分の人生を自由に選択するための「思考の冒険」。メタ認知、ソクラテス、母語、トークン…。新進気鋭の教育者が、古今東西の偉人を含む100のキーワードを解説する。
#学問 #思考
きみはスゴイぜ!
マシュー・サイド/著 -- 飛鳥新社 -- 2020.7 -- 197p
一生使える「自信」をつくる本
勉強、スポーツ、趣味で「スゴイ子」はどこが違うのか? 成長し続けるマインドセット、自信をつける科学的方法、効率のいい努力の仕方など、12歳で身につけたい自己肯定感をマックスにするとっておきのノウハウを紹介する。
#自己肯定感 #自信
障害がある子どもの文・文章の理解の基礎学習
宮城 武久/著 -- 学研プラス -- 2018.8 -- 291,29p
文をつくる 文章の内容がわかる
学研のヒューマンケアブックス
障害がある子どもが「文や文章を読んで意味と内容がわかるようになる」ための学習方法を詳しく解説。助詞を用いた文の構成から、具体的な学習方法、ことばがけまで、わかりやすく説明する。後ろから読む例文集付き。
#障がい児教育 #作文
10年後の子どもに必要な
「見えない学力」の育て方
木村 泰子/著 -- 青春出版社 -- 2020.11 -- 214p
「困った子」は「困っている子」
「人に迷惑をかけてはいけない」と教えると、子どもは人を排除するようになる-。「不登校」も「問題児」もいない公立小学校の元校長が、親と子の新常識を明かす。子どもが変わるエピソードが満載。
#家庭教育 #声掛け
子どものドキッとする
性の質問にちゃんと答えるBook
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2022.2 -- 24p
プライベートゾーンってどこ? セックスってどうすることなの? 性に関する子どもの質問をついはぐらかしてしまうパパ・ママに向けて、命のふしぎに迫り、子どもの自己肯定感を育む具体的な言葉がけを提案する。
#性教育
わたしからはじまる心理的安全性
塩見 康史/著 -- 翔泳社 -- 2023.8 -- 255p
リーダーでもメンバーでもできる「働きやすさ」をつくる方法70
いろいろな立場で心理的安全性の実現に取り組む手法を学べるTips集。図やイラストを交えて、実践方法をわかりやすく解説。個人、チーム規模から組織規模のものまで網羅的にカバーする。
#コミュニケーション #組織経営
「人に迷惑をかけるな」
と言ってはいけない
坪田 信貴/著 -- SBクリエイティブ -- 2021.7 -- 238p
「迷惑をかけるな」では自分から動けなくなる、「やればできるよ」では挑戦しなくなる-。つい言ってしまいがちな一言が、子どもにとっては逆効果に。「自分で考えて動ける子」を育てる心理学的に正しい声かけを紹介する。
#声掛け #家庭教育
動物がくれる力
大塚 敦子/著 -- 岩波書店 -- 2023.4 -- 10,267,7p
教育、福祉、そして人生
犬への読み聞かせは子どもを読書へ誘い、生きづらさを抱える子どもは傷ついた動物をケアする中で育つ。病気のある人や高齢者も、犬や猫と共に心豊かな日々を過ごす。人と動物のポジティブなかかわりとそこにある可能性を綴る。
#社会福祉 #アニマルセラピー #教育
児童虐待と児童保護
町野 朔/共編 -- Sophia University Press上智大学出版 -- 2012.3 -- 299p
国際的視点で考える
諸外国の児童虐待防止システムを解説。アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、韓国、台湾の児童虐待・児童保護への対応の一端を紹介し、日本の児童虐待・児童保護問題の課題と対応策を浮き彫りにする。
#児童福祉 #児童虐待
インスリン注射ってなんだろう?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2023.2 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
すい臓の「スイッチ」と、インスリンペンの「リンリン」が案内役になって、インスリン注射のはたらきや使い方、糖尿病などについて解説。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Using insulin
#糖尿病 #インスリン #バリアフリー
「ほんとのこと」は、
親にはいえない
木村 泰子/著 -- 家の光協会 -- 2021.3 -- 191p
子どもの言葉を生み出す対話
対話の目的は何なのか、どうすれば対話が成立するのか。45年間教育の現場で子どもたちと対話を重ねてきた著者による、親と子のコミュニケーション論。子どもとの関係に悩む大人に、子どもとの関わり方で大切なことを伝える。
#親子 #対話
発達障害のある人が受けられる
サービス・支援のすべて
嬉泉/監修 -- ナツメ社 -- 2023.7 -- 223p
発達障害のある人が受けられるサービス・支援を、幼児期から就学期、就労期、親なき後への準備まで、ライフステージごとに、カラーのイラストや図表とともにわかりやすく紹介する。事例や発達障害の療法なども掲載。
#発達障がい #福祉サービス
エピペン注射ってなんだろう?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2023.2 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
気管の「スースー」と、エピペンの「ペンペン」が案内役になって、エピペン注射のはたらきや使い方、アナフィラキシーなどについて解説。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Using an auto‐injector
#アレルギー #バリアフリー
「食事の習慣」
を変えれば心が疲れない!
安藤 俊介/著 -- 辰巳出版 -- 2021.2 -- 190p
イライラしないための“アンガーマネジメント的”食事術
心が疲れないために大事なのは、「何を食べるか」ではなく、「どう食べるか」。普段食べているものを変えずに、「食べ方を変える」ことで、心が疲れなくなる方法を紹介する。ニューノーマル時代の心の整え方も収録。
#食生活 #アンガーマネジメント
きみの人生はきみのもの
谷口 真由美/著 -- NHK出版 -- 2023.1 -- 154p
子どもが知っておきたい「権利」の話
親にも先生にも友だちにも話せない問題でこまったとき、声をあげてほしい-。「心」「体」「お金」にかかわる悩みや問題を取り上げ、子どもの「権利」を紹介しながら解決への道を示す。相談先や専門機関も掲載。
#児童福祉 #人権 #子どもの権利条約
吸入器ってなんだろう?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2023.2 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
肺の「ハッチ」と、吸入器の「キュウタ」「キュウスケ」が案内役になって、肺のはたらきやぜんそく、吸入器について紹介。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Using an inhaler
#吸入療法 #喘息 #バリアフリー
この世の中を動かす暗黙のルール
岡田 尊司/著 -- 日本図書センター -- 2020.9 -- 223p
人づきあいが苦手な人のための物語
失業し、自殺を図った若者は、助けられたのちに入院した精神病院でひとりの奇妙な老人と出会い…。生きにくさを感じている人に向けて、人生の幸不幸を左右する8つの「暗黙のルール」を物語形式で伝える。
#コミュニケーション #人間関係
奇跡のフォント
高田 裕美/著 -- 時事通信出版局 -- 2023.4 -- 237p
教科書が読めない子どもを知って-
UDデジタル教科書体開発物語
読み書き障害でも読みやすいフォントはどう生まれたのか? 「UDデジタル教科書体」を開発した書体デザイナーが、その試行錯誤と工夫を明かす。多様性の時代における教育・ビジネスのヒントになる一冊。
#ユニバーサルデザイン #フォント
ストーマパウチってなんだろう?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2023.2 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
大腸の「だいちゃん」と、ストーマパウチの「トーヤン」が案内役になって、大腸のはたらきやストーマパウチについて紹介。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Using a colostomy bag
#ストーマパウチ #バリアフリー
健康的で清潔で、
道徳的な秩序ある社会の不自由さについて
熊代 亨/著 -- イースト・プレス -- 2020.6 -- 314p
社会の進歩により当然のものとなった通念は、人々に「自由」を与えた一方で、個人の認識や行動を「束縛」しているのではないだろうか。健康、少子化、清潔、空間設計などを軸に、令和時代ならではの「生きづらさ」を読み解く。
#社会問題 #生きづらさ
虹色のチョーク
小松 成美/著 -- 幻冬舎 -- 2017.5 -- 221p
社員の7割が知的障がい者のチョーク工場「日本理化学工業」が業界トップシェアを成し遂げ、“日本でいちばん大切にしたい会社”と呼ばれる理由とは。家族の宿命と経営者の苦悩、同僚の戸惑いと喜びを描いたノンフィクション。
#障がい者雇用 #知的障がい
ペースメーカーってなんだろう?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2022.12 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
心臓の「しんちゃん」と、ペースメーカーの「ペスモ」が案内役になって、心臓のはたらきやペースメーカーについて紹介。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Having a pacemaker
#ペースメーカー #バリアフリー
野の医者は笑う
東畑 開人/著 -- 誠信書房 -- 2015.8 -- 299p
心の治療とは何か?
ふとしたきっかけから怪しいヒーラー達の世界に触れた臨床心理士が、彼らの話を聴き、治療を受けて回ることに。次から次へと現れる不思議な治療! フィールドワークで心の治療を根底から問い直す一冊。
#心理療法 #医療人類学
性をはぐくむ親子の対話
野坂 祐子/著 -- 日本評論社 -- 2022.12 -- 164p
この子がおとなになるまでに
子どもとおとなが一緒に性について学び、対話するヒントを紹介。年代ごとの子どもの発達の様相、安全・安心な関係づくりについて解説するとともに、子どもの性や安全に関するおとなの不安や悩みを取り上げる。
#性教育
義肢をつけたらどうなるの?
ハリエット・ブランドル/作 -- ほるぷ出版 -- 2022.2 -- 24p
からだとはたらくどうぐたち
足の「アルク」と、義足の「ソッキー」が案内役になって、義肢のしくみやつけ方、やっていいこと・ダメなことなどを紹介。当事者の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。
原タイトル:Wearing an artificial limb
#義肢 #バリアフリー
心理的安全性をつくる言葉55
原田 将嗣/著 -- 飛鳥新社 -- 2022.8 -- 305p
最高のチームはみんな使っている
心理的安全性とは、誰もが率直に思ったことを言い合えること。チームで最高の成果を出すために、職場で使う言葉から変えよう。日本の職場でよくある場面を厳選し、言葉という媒体を通して心理的安全性を高める手法を伝える。
#リーダーシップ #チームワーク
